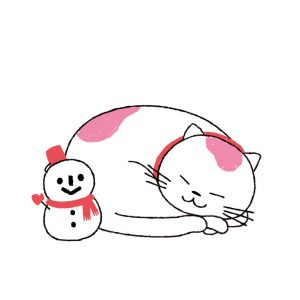行政書士とは
「街の法律家」とも言われる「行政書士」ですが、具体的にはどんな仕事ができるヒト?
よく聞かれますが、正直簡単に説明するのは簡単ではありません。
ここではそんな分かりにくい行政書士の業務を、少しご紹介させていただきます。
根拠となる法律
まずは根拠法である行政書士法の第1条の2はこのようになってます。
いきなり、読みにくい条文ですね。
読みにくいので邪魔な括弧内を削除
多少分かり易くなったと思います。官公署とは、役場的なところを包括した呼び名ですが、公務員が働いている場所といった認識でもOKです。
・「官公署に提出する書類」というと、数え上げればキリがないくらいあり、よく行政書士の業務は程射範囲が広いと言われる根拠の一つがここにあります。
「その他権利義務に関する書類」の一例もざっと以下の様にあります。
→ 賃金の請求にかかる内容証明
→ 契約解除にかかる内容証明
→ 男女問題にかかる内容証明
→ 各種契約書
→ 会社設立のための定款文書作成
→ NPO法人設立のための手続き
→ 建設業許可に必要な手続き
→ 飲食業や風営業に必要な許認可の手続き
→ 車庫証明・名義変更の手続き
→ 外国人のための在留資格手続き
→ 遺言・相続に必要な手続き
等々
「事実証明に関する書類」とは、上記権利義務を証したり主張する際、併せて必要となる事実を証明する書類のことです。
例えば、店内の図面や事故現場の現況証明など。
続いて、次の条文も欠かせません。
ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
1、前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和24年法律第205号)第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
2、前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
3、前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
小難しいことが書かれていますが、要はこちらも要約すると以下3点の内容しかありません。
2.遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等
3.上記1.、2.以外の、成年後見、ADRなどの新しいサービス
これらの中には行政書士にしかできない「独占業務」とされている業務が多くあります。
(他士業法に定められた例外も存在します)

そして、国家資格者である行政書士が行う「独占業務」ということは、その資格がなければ他の人は業として行うことが出来ないことを意味し、それを犯してしまうと罰金や懲役といった罰則を受けます。
どうでしょうか。なんとなく行政書士についてお分かりいただけましたでしょうか。(なんとなくでいいと思います)
ざっくりとした紹介になりましたが、行政書士について少しでも理解が得られましたら幸いです。
最後に、最も重要な行政書士法の1条をご紹介します。